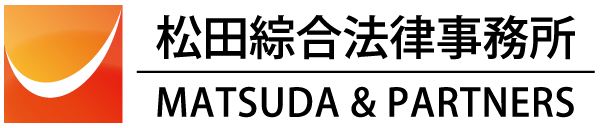M&P Legal Note 2025 No.11-1
セクハラ、性犯罪・性加害のリスクが企業価値に直結する
2025年10月20日
松田綜合法律事務所
弁護士 鈴木みなみ(東京弁護士会)
<目次>
2 よくあるご相談
3 ハラスメントと企業価値
4 セクハラ調査の難しさ
5 ワンストップ対応の必要性(松田綜合・労務チームができること)
<このリーガルノートに関連する法務>
1 セクハラリスクは対岸の火事ではない
最近、セクハラが原因で企業の役員や自治体の首長・議員が辞任する、企業がセクハラの対応を放置したことで週刊誌にリークされる等、セクハラが関係したニュースを目にすることが多いのではないでしょうか。それだけでなく、一部の報道では、セクハラが性犯罪・性加害であることを前提に、よりセンセーショナルに報道される事案も増えています。また、教師の生徒に対する性加害が立て続けに報道されたことも記憶に新しいのではないでしょうか。
また、厚生労働省の統計によれば、令和5年に全国の労働局に寄せられたセクハラに関する相談件数は7414件であり、また、セクハラの措置義務に関し、労働局が是正指導した件数は1575件と、いずれも令和4年より増加しています。セクハラについて予防・防止に力を入れている企業も増えていますが、予防・防止が功を奏しているわけではない状況です。
セクハラに関するショッキングなニュースは、どの企業にとっても「対岸の火事」ではありません。統計上セクハラの相談件数が増えていることを踏まえれば、企業としては、セクハラ・性加害について、予防だけでなく、一定数発生することを前提とした対策についてもあらかじめ検討しておくことが必要です。
2 よくあるご相談
以下は、セクハラ・性加害関係でよくご相談がある事例やニュースなどにもなった典型的な例です。特に人事・総務の担当者の方は、一度は頭を悩ませた事案や類似事案が1つはあるのではないでしょうか。
①従業員が不同意性交で(または、不同意わいせつで、痴漢で)逮捕された。
②ある従業員が、他の従業員に対し、スマートフォンで盗撮していた。または更衣室やトイレにカメラを仕掛けていたことが判明した。
③懇親会のあと、上司が部下に対し、酒に酔った勢いで胸を触った(キスをした、抱き着いた)。
④従業員が自分の体液を他の従業員の飲み物に入れた。
⑤ある従業員が、他の従業員に対し、プライベートを執拗に聞き出そうとした。
⑥取引先との会議や宴席の場で、取引先の従業員に対し、「かわいいね」「結婚しているの?」などと発言をした。
⑦従業員から、接客などの際に顧客からセクハラを受けたとして、会社として対応をしてほしいとの申し入れがあった。
⑧従業員同士が不倫をしているなどとして、通報窓口に通報があった。
⑨従業員が私傷病で休職し、復職のために面談を行うと、「実は休職の理由は社内のセクハラであった」という話をし始めた。
⑩上司が、男性(女性)だけを優遇し、女性(男性)に対して合理的な理由なく叱責することが日常的に行われ、目に余る。
特に②について、近時では、スマートフォンが普及し、写真撮影の敷居が低くなったことに伴って、安易な気持ちで盗撮を行う者が後を絶ちません。盗撮は、以前まで痴漢と同じく地方自治体の迷惑防止条例違反という位置づけでしたが、令和5年7月13日に刑法の特別法である性的姿態等撮影等処罰法が成立し、性的姿態等撮影罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が新設され、刑法犯になりました。また、同日、刑法も改正され、不同意性交罪、不同意わいせつ罪等、性犯罪の厳罰化が図られました。(なお、不同意性交罪、不同意わいせつ罪の現況についてはこちらのリーガルノートもご参照ください。
このような法改正状況を踏まえると、これまで「セクハラ」と言われていたものの一部は、現在では「性犯罪」として対応しなければならないものとなっています。セクハラはこれまでも深刻な企業リスクの一つでしたが、令和5年の刑法改正以降は、セクハラに留まらず「犯罪行為」であることを前提とした対応が必要です。別の言い方をすれば、セクハラは端的にコンプライアンス違反であるといえます。
さらに、ハラスメント指針において、取引先の従業員や顧客からのハラスメントについてもカスタマーハラスメント(カスハラ)として対応をしなければならない旨が記載されています。そのため、⑦のような接客時に顧客から受けたセクハラについても企業としては適切な対応が求められます。さらに、⑤のような取引先との関係では、自社の従業員が被害者となった場合に従業員を守るのはもちろんのこと、自社の従業員が取引先の従業員に対しハラスメントの加害者にならないよう、指導教育することが求められています。特に、取引先からのハラスメント/取引先へのハラスメントは、ビジネスと人権の文脈からも問題になることがあります。
3 ハラスメントと企業価値
このように、セクハラはもはや重大なコンプライアンス違反であり、特にレピュテーションリスクが高い事案です。上場企業で、セクハラについてマスコミで報道されたり、SNSで炎上したりすれば、株価に直結します。また、上場企業でなくてもセクハラが企業内で問題になれば、関係者の退職(人材流失)やモチベーションの低下による生産性の低下が懸念されます。このように、セクハラは、直接・間接に企業価値に影響することになります。
企業が、ハラスメントについて法令上求められる対応は、パワハラ、セクハラ、マタハラ共通で以下の4点です。
①研修の実施や周知啓発等、ハラスメントの予防
②相談窓口の設置及び適切な運営
③事案発生の際の迅速かつ適切な調査
④被害者、関係者等のプライバシー保護
ニュースになるような事案の多くは、事案そのものの深刻さがクローズアップされる場合も多いですが、「③事案発生の際の迅速かつ適切な調査」に何らか問題があったケースが散見されます。逆に、セクハラや性加害が発生し、それが一時的にマスコミに報道され、またはSNSが炎上したとしても、迅速かつ適切に対応すれば企業価値を大きく毀損する事態は避けられることが多いです。
4 セクハラ調査の難しさ
しかし、迅速かつ適切なセクハラ調査をするにあたって、様々な困難が伴います。
まず、セクハラについて、会社の担当者が被害者にヒアリングをする場合、意図せず不適切な質問をしてしまう場合や、逆に遠慮がちな質問をした結果、事実確認に過不足ない事実を確認できない結果、繰り返しの質問を行ってしまい、被害感情を損ねてしまうなど、二次被害(セカンドハラスメント)のリスクが懸念されます。
また、被害者は、セクハラ被害によって適応障害やうつ病等メンタルヘルス疾患を発症している場合も多くあり、会社担当者が被害を軽視するような発言をすれば、より病状が悪化することも想定されます。
さらに、プライバシーの観点から、第三者へのヒアリングについても慎重に行うことが必要です。被害者によっては、調査開始が悟られることによって加害者から報復されることを恐れ、調査を関係者にも知られないように行ってほしいという要望が出て、担当者は調査にあたって難しい立ち回りを要求されることもあります。
加えて、特にセクハラは、被害申告の心理的なハードルから、実際の被害から長期間経過後に申告がなされることがあります。その場合、時間の経過によって関係者の退職や裏付け資料の消失などが生じやすく、やはり調査のハードルは上がります。
このように、セクハラ調査は内容がセンシティブであればあるほど難しいものになりますが、会社が調査で対応を誤ったことによって、本来加害者に向いているはずの怒りが会社に向いてしまい、被害者との間で深刻な紛争に陥ってしまう事案も散見されます。そのような場合、被害者による労災申請、会社に対する損害賠償請求だけでなく、場合によってはSNSへの書き込み、マスコミへのリーク、被害者による訴訟提起時の記者会見の実施等、レピュテーションリスクも懸念されます。
5 ワンストップ対応の必要性(松田綜合・労務チームができること)
松田綜合・労務チームは、企業刑事法チームと連携して、以下の点にワンストップで対応が可能であるほか、クライアント様のニーズに応じたカスタマイズも可能です。
現在お困りごとがある企業様のみならず、今後の対応への備えにご関心のある企業様は、是非一度お問い合わせフォームからご連絡ください。
1)初動
事件の見通しに関するアドバイス、従業員が逮捕された場合や、警察に被害届が出ている場合の警察との連携
2)調査
被害者・関係者・加害者へのヒアリング、メッセージアプリや録音データ等の分析を含む事実調査、調査報告書の作成
3)加害者への対応
懲戒処分の軽重に関するアドバイス、懲戒処分のための弁明の機会付与の立ち合い、懲戒処分通知書の作成、懲戒処分通知の立ち合い、懲戒処分を争う際の裁判対応等
4)被害者への対応
被害者ケアに関するアドバイス、被害者が労災申請をした場合の労基署対応、紛争となった場合の紛争対応
5)再発防止
研修講師の担当。なお、研修は、全社員向けの一般的なもの、主に管理職向けのグループワーク付きのものだけでなく、相談窓口担当者や人事担当者向けに、ハラスメント調査のポイントやノウハウに関する研修も可能です。
6)第三者委員会対応、マスコミ対応
ステークホルダー等から第三者委員会または特別調査委員会の立ち上げを要求された場合の受嘱、プレスリリースに関するアドバイス、記者会見の立ち合い等のマスコミ対応
以上
<このリーガルノートに関連する法務>