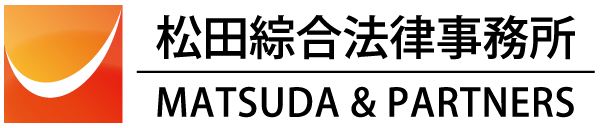M&P Legal Note 2025 No.3-1
「企業刑事法務チーム」のご紹介①
~企業活動と刑事事件の交錯するところ~
2025年5月26日
松田綜合法律事務所
弁護士 片岡 敏晃(東京弁護士会)
1 はじめに
私は松田綜合法律事務所パートナー弁護士の片岡敏晃と申します。
検事を約30年務めた後、4年前から弊所で弁護士として仕事を始め、現在は、リスクマネジメント、不正調査、そして、弊所「企業刑事法務チーム」のメンバーとして企業に関わる刑事法務等の業務を行っています。
企業において、企業やその役職員が関係する刑事事件が発生したり、刑事処分を受けたりすることが重大事であることはもちろんですが、刑事に関わる事案は、実際に警察が動くような大事に至らなくても、実に様々なインパクトを及ぼすものです。
そして、刑事事件を捜査処理する立場から弁護士に転じて意外だったのは、企業は、加害者、被害者、関係者として刑事事件に関わる場面がことのほか多いということです。
今回は、弊所ニュースレターにおいて、2回に分けて、企業刑事法務チームについて紹介いたします。
1回目(本号)は、企業活動と刑事事件が交錯する場面を概観して、2回目(次号)は、実際に刑事事件が発生した場合に起こることや、そのような場合に企業刑事法務チームがどのような対応を行っているかについてお話しします。
2 企業と刑事事件の接点
一般に、企業は社会に有益な価値を創造することにより利益を上げることを目指しているといえますが、そうした善良な企業も、「人」の集まりである以上、ときに過ちを犯したり、また、犯罪に巻き込まれたりする可能性があることは否定できません。
また、その場合の結果の重大性を考えると、平素から、自社にどのような刑事事件リスクがあるかを考えておくことは意義のあることと思います。
参考までに、主体(企業自体か役職員か)と立場(加害者か被害者か)を軸に、企業やその役職員が刑事事件に関わる場面を整理してみます。
I. 企業が加害者となる場面:
独禁法違反(談合等)、金商法違反(有価証券報告書の虚偽記載等)、税法違反(法人税、消費税の脱税など)、各種業法違反、廃掃法違反(廃棄物の不法投棄等)、不正競争防止法違反(無体財産権の侵害等)、労働関係法令違反(賃料不払い等)、労働安全衛生法違反(工場内の死傷事故等)など。
II. 企業が被害者となる場面:
窃盗、詐欺、建造物損壊・器物損壊、業務妨害、ネット上での誹謗中傷、役職員による横領・背任など。
III. 役職員が加害者となる場面:
業務関係では、Ⅰの各犯罪の行為者として個人の責任が問われる場合のほか、贈収賄、業務上過失致死傷、横領・背任、窃盗など。また、業務外ではあらゆる犯罪類型があり得る。
IV. 役職員が被害者となる場面:
業務関係では業務上過失致死傷、暴行、傷害、性犯罪、業務外ではあらゆる犯罪類型があり得る。
なお、発生する事象は、上記ⅠないしⅣのカテゴリのいずれか一つに当てはまる場合だけでなく、役職員の行為(Ⅲ)により企業(法人)も刑事責任を負う場合(Ⅰ)や、同僚間のトラブルで加害者と被害者が同じ企業の役職員である場合(Ⅲ、Ⅳ)など、一つの事象が複数のカテゴリに該当する場合もあり、むしろその方が多いと思われます。
3 刑事事件が発生したときに起こること
刑事事件も不祥事も、大概、何の前触れもなく突然起こります。もちろん、実際には、長い時間をかけて目に見えないところで下地が形成されている場合が多いのですが、それは後から分かることです。
証拠は捜査機関に押収されてしまい、ときには事情を知る当事者が捜査機関に身柄拘束されているなど、自分の組織のことながら分からないことが多い中、報道が先行し、その報道により具体的嫌疑や組織が置かれている状況を知るということも少なくないように思われます。
このように見通しがきかない中であっても、事態は進行し、企業として、対外的、対内的に対応を迫られることになります。
役職員が逮捕されたことが報道されたら、企業として何かコメントすべきでしょうか、コメントするならどのような内容にすべきでしょうか?
あるいは、まだ組織内の誰も知らない状況で、役職員の犯罪行為に関する情報を得た場合に、まず何をすべきでしょうか?
また、加害者も被害者も同じ組織の役職員であった場合に、真逆の立場にある関係者に対して、どう対応すべきでしょうか?
決まった答えはありません。
原則的なことを挙げることは可能ですが、その具体的対応は、まさに一つひとつの案件の内容によって変わってくるものです。
次号では、求められる対応をモデル的に示し、企業刑事法務チームの取組等を紹介していきます。