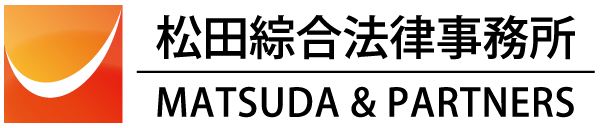M&P Legal Note 2025 No.1-1
内部通報関連法務(3)~公益通報者保護制度検討会の報告書を踏まえた今後の法改正の見込み~
2025年1月27日
松田綜合法律事務所
弁護士 柴田 政樹(東京弁護士会)
1 はじめに
2024年5月より、消費者庁において公益通報者保護制度検討会(以下「検討会」といいます)が開催されておりました。この検討会は、直近の法改正(2020年改正)における附則において、改正法施行から3年を目途として検討を加えた上で必要な措置を講じることとされていたことに基づくものです。
この度、検討会での議論状況を踏まえた報告書[1](2024年12月27日)が取りまとめられました。当該報告書の中では、法改正をすべき事項に関する提言がなされており、今後、これに沿った法改正が行われることが見込まれます。そこで、今回は、法改正が見込まれる事項(個別論点)とこれが実務に与える影響についてご説明させていただきます。
2 法改正が見込まれる事項(個別論点)
報告書を踏まえ、今後、法改正が見込まれる事項は以下の通りです。
| ・従事者指定義務違反に関する規制強化(間接罰等の導入)
・公益通報者の探索行為禁止の明文化 ・公益通報の妨害行為の禁止の明文化 ・公益通報を理由とする解雇・懲戒への罰則の導入 ・解雇・懲戒に関しての立証責任の転換 ・フリーランスによる公益通報の保護の明文化(通報主体の拡大) (※中小事業主への体制整備義務の適用拡大は、今後の検討事項とされました。) |
(1) 従事者指定義務違反に関する規制強化(間接罰等の導入)
報告書では、公益通報対応業務従事者に関する従事者指定義務の履行徹底を目的に、消費者庁の行政措置権限を強化し、当該義務違反に対する間接罰等を導入すべきとされています。
従事者指定義務は、現行の公益通報者保護法(以下、「現行法」といいます)における事業者(ただし、中小事業主は除く)の義務ですが(現行法11条1項)、これに違反したことに対する直接的なペナルティ(刑事罰)は規定されていません。もちろん、当該義務違反に対して行政上の措置(報告徴収、指導・助言、勧告、勧告に従わない場合の公表)を行うことは可能です(現行法15条、16条)。しかしながら、当該義務の履行を徹底するためには、行政措置では十分とは言い難いということで、上記提言がなされています。具体的には、現状の行政措置に加え、事業者が勧告に従わない場合の命令権や命令を受けても是正しない場合には刑事罰(間接罰)を科すという建付けが示されています。
仮に、上記法改正が行われたとしても、従事者指定義務は既に事業者の義務であるため、新たな義務が加わるということではありません。そのため、実務に与える影響は大きくないといえます。
ただ、現時点で、従事者指定義務を怠っている企業に関しては、現行法の枠内での行政措置を受ける可能性が高まったと言い得るため、早急に、義務履行をしておくことが必要です。といいますのも、上記提言は、消費者庁が従事者指定義務の履行状況を問題視し、十分な履行を促すべきとの考え方を改めて示したものですので、法改正を待たずとも、現行法の枠内でより厳しく行政上の措置が行われることが想定されるためです。
なお、従事者指定義務を怠っている場合には、役員の善管注意義務違反に基づく損害賠償責任(会社法423条1項)が問題になり得ますので、役員の責任という観点でも、適切な義務履行が必要であることを再確認いただければと思います。
(2) 公益通報者の探索行為禁止の明文化
報告書では、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為(探索行為)を禁止する規定を設けるべきであるとされています。
現行法では、探索行為の禁止は法律上の明文規定はありませんが、その指針(以下「法定指針」といいます)において、体制整備義務(現行法11条2項)の一環として、「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査ができないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」こととされています。そのため、現行法においても、探索行為が行われた場合には行政措置の対象になり得るものであるため、実務への影響は大きくないと考えます。
なお、探索行為禁止に違反した場合における罰則を導入すべきとの意見もあったようですが、導入は見送られ、今後の検討事項とされました。
(3) 公益通報の妨害行為の禁止の明文化
報告書では、正当な理由なく、公益通報を妨害する行為(公益通報をしないことを約束させること、公益通報をした場合には不利益な取り扱いを行うことを示唆することなど)を禁止し、これに違反する法律行為(契約書や誓約書の締結)を無効とする規定を設けるべきであるとの提言がされています。
上記提言は、これだけを見てしまうと、実務上の影響は大きくないようにも思われます。といいますのも、労働者との間で、入社時の雇用契約書や誓約書、秘密保持契約書等において、公益通報をしないことを約束するような文言を入れているケースは極めて稀であるためです。
他方で、ある従業員が内部通報(1号通報)をしたケースでは、事業者として、内部で調査及び是正をするまでの間は、外部通報(行政機関や報道機関等)を控えて欲しいと考える場面が生じ得ます。そのため、上記提言は、内部通報(1号通報)が行われたようなケースで、実務上の影響が生じるものといえます。法改正後は、このようなケースにおいて、通報者との間で締結する誓約書等において、漫然と外部通報等を行わないことを約束させるのではなく、「正当な理由」がある場合は義務が免除されることを明記しつつ、「正当な理由」の具体的なケースを例示するという対応などが考えらます。
(4) 公益通報を理由とする解雇・懲戒への罰則導入
報告書では、公益通報を理由とする不利益取扱いのうち解雇及び懲戒に関しては、これを行った事業者及び個人に対して刑事罰を科す旨の規定を設けるべきと提言されています。
現行法において、公益通報を理由とする不利益取扱いは禁止されており(現行法3条、5条)、これに違反した法律行為(解雇、懲戒、その他人事権の行使等)は無効となります。これらは民事的な効力に留まるところ、公益通報者保護制度に対する社会一般の信頼と通報者個人の職業人生や生活の安定を守るため、刑事的な効力(刑事罰)を定める必要があるとの方向性を示したものです。
刑事罰の対象を解雇及び懲戒に限定しているのは、構成要件の明確性及び当罰性の観点に基づく判断とのことです。公益通報者保護法で禁止される不利益取扱いには、法律行為のみならず事実上の行為(仕事を与えない、過重な仕事を与える、雑作業をさせるなど)が含まれると幅広に解釈されていますので[2]、一定の法律行為に限定するということは合理的であるといえます。ただ、懲戒には、雇用契約終了の効果を持つもの(懲戒解雇、諭旨解雇)、その待遇や給与額に影響を与えるもの(降格、出勤停止、減給)、将来を戒めるもの(譴責、訓戒等)など、不利益の程度に大きな差があるため、これらを一括りに刑事罰の対象とすることには、当罰性の観点から疑問が残ります。また、検討会でも意見が挙がったようですが、実務上は、特に役職者の非違行為に関しては、懲戒処分としての降格ではなく、人事権行使としての降格を行うケースもありますので、刑事罰のリスクを回避するために後者を選択するという事態が横行することも想定されます。したがいまして、上記の扱いが適切な整理となっているか、より慎重な判断が必要であるようには思います(検討会において十分に議論された結果であろうとは存じますが。)。
刑事罰が科される主体に関しては、事業者のみならず、意思決定に関与した者(個人)を処罰対象とするとされています。ここでいう個人は、意思決定に関与する権限のある者を想定しているようですが、直接的な権限がなくとも、意思決定に関与した者には刑法の共犯規定により処罰対象となり得る、とのことです。報告書の文面上は、広く処罰対象を想定した内容となっていますので、注意が必要です。
今回の報告書の中で実務上の影響が一番大きいのは、上記提言であるものと考えます。すなわち、この点の法改正が行われた場合、労働者の通報行為(特に、企業内の不正やコンプライアンス違反を行政機関や報道機関等の外部に告発するような行為)を契機とした解雇や懲戒を検討するにあたって、民事的なリスク(解雇や懲戒処分が無効と判断されるリスク)のみならず、刑事的なリスクを十分に考慮した判断が必要となります。もちろん、刑事罰の有無にかかわらず、公益通報者保護法により保護される状況において、通報者への不利益取扱いを行うことは許容されるものではありません。しかしながら、労働者の通報行為は、企業秘密の漏洩や企業の名誉・信用を毀損する側面もあるため、形式上は懲戒事由等に該当し得るものであって、企業として漫然と放置をすることができるものではありません。また、公益通報として保護がなされる事案か否かという点は、その判断が極めて難しく、究極的には裁判所の判断を待たざるを得ないという面もあります。実際に、昨今も、通報行為を契機とした解雇や懲戒処分が裁判の場で争われ、その有効性について判決に至る事案が複数生じています。このような事案の中には、地方裁判所と高等裁判所とで判断が分かれたようなものもあります[3]。
以上の通りですので、公益通報を理由とする解雇・懲戒への罰則導入は、企業の権限行使に事実上の制限を課すことにつながるものと考えます。報告書によると、主要先進国における法制度の状況等も踏まえた上での方針のようですが、企業にとっては極めて厳しい制限ではあります。企業として、公益通報に対する保護の在り方や意識を変えていかなければいけない時代になってきていると言わざるを得ないものと存じます。
(5) 解雇・懲戒に関しての立証責任の転換
報告書では、解雇及び懲戒の有効性が争われる場合において、公益通報者保護法が適用されるための要件のうち、「公益通報を理由とすること」の立証責任を事業者に転換すべきとされています。
本来、裁判(民事訴訟)においては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うとされているため、公益通報者保護法が適用されるための要件は、原則として、通報者が立証責任を負うことになります。報告書では、このような原則論を修正した例外を設けるべきとするものです。これは、事業者側に情報や証拠資料が偏在していることから、通報者に立証上の大きな負担を被らせているということを踏まえた方針のようです。
実際の裁判例を見ても、通報行為を理由とするといえるかどうかを巡って争われている事例も存在するため、この点は実務に相応の影響を与えるものと考えられます。企業側としては、通報行為と時間的に近接する状況で解雇及び懲戒を行うようなケースにおいては、「公益通報を理由とする」ものではないことを立証できるようにしておく必要があります。具体的には、解雇及び懲戒の通知書の記載内容やその手続きにあたって留意が必要といえます。
なお、この立証責任の転換は、公益通報をした日から1年以内の解雇及び懲戒に限定すべきであるとされています。
(6) フリーランスによる公益通報の保護の明文化(通報主体の拡大)
報告書では、公益通報の主体に、業務委託関係にあるフリーランス(契約関係終了後1年以内の者を含む)を追加し、公益通報を理由とする不利益取扱い(業務委託契約の解除、取引数量の削減、取引停止、報酬の減額等)を禁止する旨の規定を導入すべきとされています。
昨今、フリーランスとしての働き方が浸透する中で、2024年11月よりフリーランス保護法が施行されていますので、時代の趨勢に合わせた提言といえます。
実務上の影響としては、内部通報規程における通報者の範囲を修正する必要が生じますので、規程整備の対応が必要となります。
なお、フリーランス保護法が内部通報制度に与える影響については、以下のLNもご参照ください。
(2024-6-1 内部通報関連法務(2)~フリーランス保護法が内部通報制度に与える影響~)
3 最後に
今回は、検討会の報告書を元に、今後の法改正が見込まれる事項と実務上の影響について取り上げました。ただ、検討会の議論状況を見ると、今回は引き続きの検討事項とされたものについても、近い将来、法改正に向けた動きが進むことが予想されます。企業としては、より一層、内部通報制度の適切な構築や運用が求められる時代に突入していくということを見込んで、早い段階で、内部通報制度の見直し(社内的な周知、窓口担当者への教育、内部通報処理業務のノウハウ蓄積等)に着手すべきといえます。
以上
<註>
[1] 令和6年12月27日付け「公益通報者保護制度検討会 報告書」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/assets/review_meeting_004_241227_01.pdf
[2] 山本隆司ほか 「解説 改正公益通報者保護法 [第2版]」(弘文堂 2023年)177頁。
[3] 検討会の資料の中に、一審と二審とで判断が分かれた事案が挙げられています。
<シリーズ:内部通報関連法務>
- 2025-4-1 内部通報関連法務(4)~濫用的通報への向き合い方及び予防策について~
- 2025-1-1 内部通報関連法務(3)~公益通報者保護制度検討会の報告書を踏まえた今後の法改正の見込み~
- 2024-6-1 内部通報関連法務(2)~フリーランス保護法が内部通報制度に与える影響~
- 2024-4-1 内部通報関連法務(1)~改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報窓口の見直し~