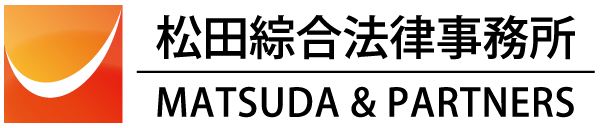M&P Legal Note 2021 No.10-1
迫られる日本企業の「ビジネスと人権」対応①
2021年10月20日
松田綜合法律事務所
弁護士 水谷 嘉伸
1 はじめに ~なぜ今「ビジネスと人権」なのか?~
今、「ビジネスと人権」に関するニュースが注目を集めている。従来、「人権」問題は、主に国家が取り組むべき課題であり、企業法務の領域では(一部の例外を除いて)正面から取り組むべきテーマではなかったように思われる。しかし、企業の事業活動が大規模化し、国境を跨ぐことが一般的になったことに伴い、企業活動による深刻な人権侵害が国際的に取り沙汰されるようになり[1]、日本においても、外国人技能実習生の劣悪な労働環境に対して国内外から批判が噴出したことは記憶に新しい。
更に、2015年9月に国連総会において採択された2030年を年限とする「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals)(以下「SDGs」という。)では、全ての人々の人権を実現することを目指す旨が前文で謳われ、SDGsの掲げる17の目標においても随所に人権課題が取り込まれているところ、SDGsは世界的なムーブメントとして日本にも押し寄せている。また、投資家サイドからも、投資判断において財務分析に加え、「環境(E)」「社会(S)」「ガバナンス(G)」の観点(非財務指標・中長期視点)も組み込むESG投資が声高に叫ばれているが、「社会(S)」の主要な部分は人権課題である。このような大きな流れとも合わさり、「ビジネスと人権」は今や企業経営におけるメガトレンドとなっていると言ってよい。そのため、企業活動において人権課題への取り組みを推進することが、事業上の取引の維持・拡大、潤沢な資金調達、優秀な人材の確保・維持、更には消費者や世論の信頼維持・向上といった会社のあらゆる側面から極めて重要となっており、企業の持続的な成長のための喫緊の重大な経営課題となっている。
そして、これは大企業はもちろん、中小企業の経営にも大きな影響を及ぼしうるテーマであるため、あらゆる企業の経営者が、「自分ごと」として理解し、率先して対応することが求められる。何も対策を打たずに放置した結果、例えば、取引先の人権侵害が明るみになり、世間的な信用低下のみならず、取引停止、投資引上げ、従業員のストライキ、消費者の不買運動等の事業に直結する様々な悪影響が発生するリスクは日に日に高まっていると言える。一方で、「ビジネスと人権」分野で取り組むべき課題は、対症療法的な小手先の対応でやり過ごせる課題ではなく、後述する人権DDや苦情対応システムの整備といった具体的な対策を実施しようとすると相当な労力・コストが発生するものが多く、それどころか、場合によっては大胆な事業転換を実行する必要性に迫られる可能性もある。そのため、これはトップマネジメントが、日本ひいては世界の情況を踏まえ、中長期的な視野をもって実行することが求められる高度な経営判断を伴うテーマであることも十分に認識する必要がある。
本連載では、日本企業に差し迫る「ビジネスと人権」の問題を深く理解できるよう、まず、「ビジネスと人権」を語るうえで肝となる「ビジネスと人権に関する指導原則」について概説する。そのうえで、世界における「ビジネスと人権」にかかる法制化の流れを説明し、後れを取っている日本の状況と日本企業の取るべき対応について述べることとする。
2 ビジネスと人権に関する指導原則
(1)指導原則の位置づけ
「ビジネスと人権」に関する様々な政策、ガイドラインや法令の源流を辿ると、2011年6月16日に国連人権理事会において採択された「ビジネスと人権に関する指導原則 (Guiding Principles on Business and Human Rights)」(以下「指導原則」という。)に行き着く。この指導原則は、ビジネスに関連する人権侵害を効果的に防止し、是正するための全世界に通用する実務的な指針を提供するものである。同原則は、国連事務総長特別代表に任命されたハーバード大学のジョン・G・ラギー教授が中心となり、様々なステークホルダーとの広範な協議・対話を経て練り上げられ、国連人権理事会において全会一致で採択されたものであり、高い説得力・正統性を有する。そのため、各国の政策や法制等の土台となっており、「ビジネスと人権」分野における最も重要な規範であると言っても過言ではない。
(2)指導原則の構成
指導原則は、全31原則によって構成され、大項目は以下の3つであり、2008年に前述のラギー教授が提案し国連人権理事会が支持した”Protect, Respect and Remedy”(保護、尊重及び救済)の枠組みを実践するものと位置づけられている。企業に直接関わるのは2番目の「企業による人権尊重責任」と3番目の「救済へのアクセス」である。
Ⅰ. 国家の人権保護義務(The State duty to protect human rights)(原則1~10)
Ⅱ. 企業の人権尊重責任(The corporate responsibility to respect human rights)(原則11~24)
Ⅲ. 救済へのアクセス(Access to remedy)(原則25~31)
そして、「企業による人権尊重責任」を果たすため、指導原則は、企業に対して以下の3つを実践すること等を求めている(原則15)。
① 人権方針によるコミットメント(原則16)
② 人権デュー・デリジェンスの実施(原則17~21)
③ 人権侵害の救済を可能とするプロセスの整備(原則22、29、31)
(3)指導原則の意義
指導原則の理解のためには、指導原則そのものをまずは一読することを推奨したい[2]。ここでは逐条的な説明に代えて、指導原則が全世界の企業の企業行動に果たしている重要な意義について述べることとしたい。
(ⅰ) 「企業」の人権尊重責任
第1に、「人権」課題の当事者に「企業」を加え、企業に人権尊重責任があると定めたことである。前述の通り、従前「人権」は主に対国家規範と捉えられていたが、指導原則により、国家のみならず、企業にも人権侵害に対応する責任があると明記された。それにより、企業は、企業活動により生まれる果実を得るだけなく、それにより生じうる「負の影響」(=人権侵害)を抑止する責務もあることが明らかにされたのである。そして、この企業の人権尊重責任は、その規模や業種を問わず全企業に適用されること、また、事業を行う国や地域を問わず適用されることが指導原則上明記されている(原則11、14、23)。
(ⅱ) 「人権」を企業の本流の企業活動自体のコンプライアンス問題に
第2に、人権対応を、企業の本流の事業活動から区別された倫理的活動から事業活動自体のコンプライアンス問題へと格上げしたことである(原則23)。従前は、企業における人権課題は、CSR(Corporate Social Responsibility)、即ち、企業の社会的責任として、慈善活動的な色彩もある倫理的活動の中に取り込まれ、企業の本流の事業活動とは区別されていることも多かったが、指導原則は、それを企業の事業活動そのものの課題として取り組むことを求めた。即ち、指導原則は、企業が収益の源泉となる本流の事業活動自体のコンプライアンス課題として、事業活動に伴う「負の影響」(=人権侵害)を特定・精査し、それを抑止・是正することを求めている。かかる取り組みは、事業活動の収益に直結し、場合によっては、事業モデルの変更・修正を迫るものであり、重要な経営課題と認識されるようなったと言える。
(ⅲ) サプライチェーンを含めた事業活動全般にわたる「人権デュー・デリジェンス」の実施を求める
第3に、企業のステークホルダーの人権への負の影響を特定、予防、軽減し、対処方法に関する説明責任を果たすためのプロセスとして、人権デュー・デリジェンス(以下「人権DD」という。)を要請している点である。人権DDは、M&Aにおけるデュー・デリジェンスとは全く異なるプロセスであり、以下のような特徴を有する。
- 「人権リスク」の査定:査定するリスクは、人権侵害の対象となるステークホルダーの人権リスクであり、会社のリスク(=企業価値を毀損するリスク)そのものではない。
- 継続的プロセス:一回きりの作業ではなく継続的(ongoing)なプロセスとする必要がある。人権リスクは事業の進展と共に変わるものだからである(原則17)。
- ステークホルダー・エンゲージメント:実効的な人権DDのためには、人権侵害にかかるステークホルダーとのエンゲージメント(関わり合い)と対話が極めて重要である。
* 「ステークホルダー」とは、企業がその人権を尊重する責任を負う利害関係者であり、自社の従業員のみならず、取引先の従業員、顧客、地域住民等を指し、より広く労働組合、NGO、株主等を含むこともある。
- サプライチェーンを含む企業活動全般の人権リスクの洗い出し:対象となる人権侵害のリスクは、自社の従業員のみならず、直接の取引先、更にはその先のサプライチェーン及びバリューチェーン全体、製品・サービスに直接関わる者全体における人権侵害のリスクも含まれ、原材料の調達先の従業員、製造場所の地域住民、更には製品・サービスの消費者の人権侵害リスクも広くカバーされる。
- 企業の事業活動、製品、サービスと「直接結び付く」人権リスクの捕捉:企業内部における人権侵害や当該企業が自ら惹起(caused by)する人権侵害のみならず、当該企業が人権侵害を助長(contributed by)する場合、更には、助長せずとも、取引関係を通じた事業活動、製品、サービスと人権侵害が「直接結び付く(directly linked to)」場合も、当該企業の人権侵害のリスクとして把握する必要がある(原則13、19)。
- リスクベースアプローチ:全ての人権リスクを網羅することは難しいことが多いため、侵害の深刻さや発生可能性を踏まえたリスクベースアプローチにて実施することが適切である(原則17, 24)。ただ、人権を保護する法令がない又は脆弱である国やその十分な執行が政府に期待できない国(いわゆる「ガバナンス・ギャップ」が大きい国)においては、人権DDの範囲・深度を拡大する必要があると考えられる。
- 「影響力の行使」による対処:人権リスクが発見された場合には、人権侵害リスクがある企業に対して有する「影響力(leverage)」を行使して、当該リスクを防止・軽減・是正することに努めるべきであり(原則19)、人権侵害リスクがある企業との取引を中止することは最後の手段と考えるべきである。取引を中止することは必ずしも人権侵害の抑止につながらないばかりか、そのリスクを増大させる恐れもあるからである。
いずれも重要な特徴であるが、法務的な観点から特に注目するべきは、人権DDの対象に①別法人であり法律的な責任は遮断されるはずの取引先のみならず直接の取引関係のないサプライチェーン・バリューチェーン上の企業による人権侵害、更には消費者や地域住民の人権侵害リスク、②企業の行為と人権侵害との間に法律上の因果関係が必ずしもあるとは言えない企業の事業活動、製品、サービスと「直接結び付く」人権リスクも含まれると考えられていることである。このような場合、自社に法的な責任はないから対応は不要とすることは誤った経営判断となる。また、人権リスクを抱える他社との取引関係を安易に断ち切ることで対処することも、人権侵害の対象となるステークホルダーの人権リスクを特定、予防、軽減するという人権DDの目的に反し、むしろ人権リスクを増大させる恐れがあり、適切ではない。ステークホルダーとのエンゲージメントと対話、そして企業による「影響力の行使」を通じた解決が求められるのである。
(ⅳ) 現地法令の遵守では足りない ~基準は「国際的に認められた人権」~
第4に、企業による人権尊重責任の対象となる「人権」は、現地法令上認められている人権ではなく「国際的に認められた人権(internationally recognized human rights)」であるとされている点である。ここで「国際的に認められた人権」とは、世界人権宣言、国際人権規約(社会権規約・自由権規約)、ILO中核的労働基準を始めとする国際人権基準に基づき定められている国際法上の人権である(原則12)。従って、例えば、法令上最低賃金の定めがない国であっても、国際法上認められている「生活賃金 (living wage)」(労働者とその家族が基本的ニーズを満たすために十分な賃金)は保障されるべきであることになる。このように、企業が現地法令を遵守するだけでは、指導原則の求める企業による人権尊重責任を果たしたことにはならない。この意味で、企業の人権尊重責任と企業の法的責任とは区別して考えなければならない。
(ⅴ) 企業にステークホルダーからの苦情に対応するシステムの整備を求める
第5に、事業レベルでの苦情対応システム(grievance mechanism)を整備する必要があるとされている点である(原則29)。これはいかに人権侵害の抑止に努めたとしても、人権侵害をゼロにすることはできない、という前提に基づき、人権侵害を受けた或いは受ける恐れのあるステークホルダーから苦情を受け付け対処するシステムの構築を求めるものである。そして、かかるシステムの構築を、指導原則は、国家や第三者機関のみならず、事業レベルでも構築することを求めている点に特徴がある。更に、指導原則は、苦情対応システムの実効性を担保するための基準として以下を掲げている(原則31)。
☑ 正当性
☑ アクセス可能であること
☑ 予測可能性
☑ 公平性
☑ 透明性
☑ 国際的に認められた人権に適合すること
☑ 継続的学習の源泉となること
☑ エンゲージメント及び対話に基づくこと
そのため、既存の通報窓口等を活用することを考えている企業は、対象者及び対象案件の変更・拡大に加えて、上記基準を満たすよう制度を改める必要がある[3]。
<注>
[1] 代表的なものとして、バングラデシュのダッカ近郊において、著名なグローバルアパレルブランドの商品を取り扱う下請縫製工場が多数入居する商業ビルが倒壊し、1000人を超える死者が発生した2013年4月24日の「ラナプラザ事件」がある。それらの下請縫製工場において、劣悪な労働環境下において労働を強制されていた労働者(多くは若年女性労働者)が事件の犠牲者となったことから、ファストファッション業界に対する世界的な批判が巻き起こった。
[2] (原文英語版)https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.31_en.pdf
(日本語訳)https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
[3] なお、上記基準に照らすと、企業内部にてシステムを構築するよりも、業界団体等を通じた企業横断的な窓口や弁護士等外部専門家による窓口を設けることが適切である場合も多いと考えられる。
<シリーズ:迫られる日本企業の「ビジネスと人権」対応>
- 2021-10-1 迫られる日本企業の「ビジネスと人権」対応①
- 2021-11-1 迫られる日本企業の 「ビジネスと人権」対応② ~世界の情勢~
- 2022-1-1 迫られる日本企業の「ビジネスと人権」対応③―1~日本の状況~
- 2022-2-1 迫られる日本企業の「ビジネスと人権」対応③―2 ~日本企業が直面するリスクと対応~
このリーガルノートに関連する法務
お問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ、ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。
松田綜合法律事務所
弁護士 水谷 嘉伸
info@jmatsuda-law.com
この記事に記載されている情報は、依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成されたものであり、教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報について法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう、また、個別な事実関係に基づく日本法または現地法弁護士の具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。