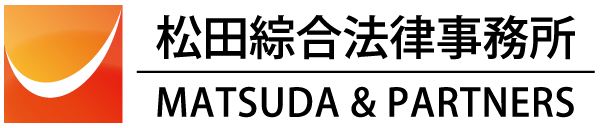M&P Legal Note 2025 No.6-1
改正法施行から2年―不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の現況と企業の対応-①
2025年7月10日
松田綜合法律事務所
企業刑事法務チーム
弁護士 勝俣 安登武(東京弁護士会)
1 はじめに
2023年7月に、これまで「強制性交等罪・強制わいせつ罪」とされていた犯罪が、「不同意性交等罪・不同意わいせつ罪」として大きくその内容が変更される法改正が施行され、早くも2年が経とうとしています。
皆様におかれましても報道等で見聞きする機会が増えたのではないかと思いますが、以下で述べますとおり、この犯罪の認知・検挙数は急激に増加しており、この種の不祥事が従来より大変重く扱われる可能性が高まっているという意味で、企業にとっても無視できない課題となっているといえます。
本稿では、2回に分けてこの不同意性交等罪・不同意わいせつ罪にフォーカスして解説します。初回は、改正からの認知・検挙数の推移を概観しつつ、改正内容のおさらい、注目の裁判例の紹介をし、次回は、企業において想定される事例やその際の対応、弊所企業刑事法務チームの対応について解説をしたいと思います。
2 認知・検挙数の急増
以下の表は、2022年から2024年の不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(改正前:矯正性交等罪・強制わいせつ罪)の認知件数、検挙人員の推移をまとめたものです。
いずれも増加傾向にあることがわかりますが、特に不同意性交等罪の認知件数は2023年には前年比63.8%増、そこからさらに2024年には前年比で認知件数は45.2%増、検挙人員数は64.6%増と急増しており、2023年7月の改正法施行以降、顕著にその数が増加していることが分かります。
不同意性交等罪(改正前:強制性交等罪)
| 2022年 | 2023年 | 前年比(%) | 2024年 | 前年比(%) | |
| 認知(件) | 1,655 | 2,711 | 63.8 | 3,936 | 45.2 |
| 検挙(人) | 1,339 | 1,875 | 40.0 | 3,086 | 64.6 |
不同意わいせつ罪(改正前:強制わいせつ罪)
| (件数) | 2022年 | 2023年 | 前年比(%) | 2024年 | 前年比(%) |
| 認知(件) | 4,708 | 6,096 | 29.5 | 6,692 | 14.7 |
| 検挙(人) | 3,067 | 3,804 | 24.0 | 4,450 | 17.0 |
※数値の引用元 警察庁webサイト「犯罪統計」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/statistics.html
3 改正のポイント(改正以前は立件が難しい犯罪だった?)
このように検挙数が急増した理由としては、法改正を受けて捜査機関が積極的に取締を行ったということも考えられますが、大きな理由は、犯罪に当たる行為の範囲が以前よりも大幅に拡大されたことにあると考えられます。
というのも、改正前の強制性交等罪、強制わいせつ罪は、その手段として「暴行」又は「脅迫」を用いていなければ罪が成立せず、かつ、強制性交等罪ではその強度も「相手の反抗を著しく困難にさせる程度」という強いものでなければならず、立件のハードルが比較的高い犯罪であったといえます。
また、法改正前でも、暴行、脅迫を用いなくとも別の方法により反抗できない(抗拒不能の)相手の状態に乗じて性交等やわいせつ行為に及んだ場合には、準強制性交等罪、準強制わいせつ罪という別の犯罪類型が規定されていましたが、ここでいう抗拒不能という要件も比較的強い程度ものが要求されていたことから、こちらも必ずしも立件が容易ではないものでした。
これが、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪に改正されることで、以下のように暴行、脅迫を用いない場合であっても広く犯罪の成立が認められることになりました。
| 下記の①〜⑧のいずれかを原因として、性交等又はわいせつ行為について、相手が同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、あるいは、相手がそのような状態にあることに乗じて、性交等又はわいせつ行為を行うこと。
① 暴行又は脅迫 |
これら新たに追加された類型については、これまでも事案によっては準強制性交等罪や準強制わいせつ罪を成立させる方向で考慮される事情にもなっていましたが、法改正によってこれらが一事情にとどまらず、明確に犯罪の成立を認める要素として位置付けられたところがポイントといえます。
これにより、特にこれまでも一定数見受けられていたものの暴行や脅迫が伴わないことから立件には至らなかったこともあると思われるアルコールによる酩酊状態(③類型)や上下関係(⑧類型)に乗じての犯行についても、明確に不同意性交等、不同意わいせつ罪として立件が可能になり、このことが検挙数の増加にも繋がっているのではないかと考えられます。
4 注目の裁判例
2025年5月14日に松山地方裁判所において、社内で同僚の女性の化粧品に自身の体液を付着させて元の場所に戻し、事情を知らない女性に使わせた行為について、不同意わいせつ罪の成立を認める判決がされました。
現時点では報道ベースの情報しかなく詳細は不明ですが、おそらくは⑤同意をしない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在を原因としたわいせつ行為として犯罪の成立が認められたものと思われます。従来は、この種の事案は、器物損壊罪等の別の罪で処罰がされる例が見られたものの、この裁判例は、このような犯人自身による被害者への間接的な接触のみであっても不同意わいせつ罪の成立が認められた点で注目されます。
次回は、企業において想定される事例やその際の対応の注意点等について解説をしたいと思います(2025年7月18日発行予定)。【https://jmatsuda-law.com/legal-note/2025-7-1/】