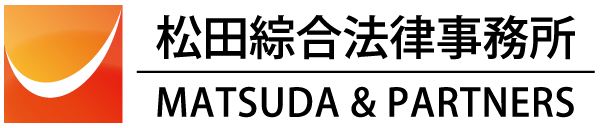M&P Legal Note 2021 No.8-2
会計限定監査役の注意義務について原審の判断を破棄し差し戻した判例(最判令和3年7月19日)
―会計と法律の交錯を考える(3)―
2021年7月29日
松田綜合法律事務所
弁護士・公認会計士協会準会員
石畑 智哉
第1 はじめに
最高裁第二小法廷は、株式会社の会計限定監査役の調査義務について判示した原審の判断を覆す判断をしました。すなわち、会計限定監査役は、特段の事情のない限り、会社の作成した会計帳簿の記載内容を信頼して計算関係書類の監査を行えば足り、会計帳簿の裏付資料を確認するなどして、会社作成の会計帳簿に不適正な記載があることを積極的に調査発見する義務を負わないとした原審の判断を破棄し差し戻しました(最判令和3年7月19日)。
本判例は、監査実務に影響を与え得るものですので、本稿にてご紹介いたします。また、本判例を踏まえて、税理士・弁護士等の職業専門家である監査役の監査業務に対して、より一層厳しい目線が向けられる可能性がございますので、特に職業専門家である監査役の皆様におかれましては、本判例にご留意頂ければと存じます。
第2 事案の概要
本件は、株式会社が当該会社の会計限定監査役であった者に対して会社法423条1項に基づき損害賠償を請求した事案であり、その概要は以下のとおりです。
- 上告人(原告)は一般製版印刷業等を目的とする資本金9600万円の株式会社。非公開会社で、取締役会設置会社・監査役設置会社。
- 被上告人(被告)は、公認会計・税理士の資格を有しており、会計事務所を開設していた。また、被上告人は、昭和42年から平成24年まで上告人の会計限定監査役(監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役)であった。
- 平成20年前後において、被上告人は上告人から税務顧問料として年額110万円、監査役報酬として年額36万円を受領していた。
- 上告人の従業員として経理を担当していた従業員(以下「本件従業員」という。)は、平成19年から平成28年にわたり、上告人の名義の当座預金口座(以下「本件口座」という。)から自己の名義の預金口座に送金する方法により、合計2億3523万円余りを横領した。
- 被上告人は、会計事務所の所員である補助者(以下「本件補助者」という。)を通じて、貸借対照表の現預金につき、会計帳簿上の額と銀行発行の残高証明書の写しを照合した。
- 本件補助者は、平成19年5月期の監査の際、本件従業員からカラーコピーで精巧に偽造された本件口座の残高証明書を提供され、それが銀行発行の残高証明書の真正な原本であると認識していた。
- 本件補助者は、平成20年5月期から平成24年5月期までの監査の際、本件従業員から白黒コピーで偽造された本件口座の残高証明書を提供され、それが銀行発行の残高証明書の写し(偽造・変造のないもの)であると認識していた。
- 上告人は、被上告人が本件従業員による横領を見抜くことができなかった点について、会社法423条1項に基づき損害賠償を請求した。
第3 原審(東京高判令和元年8月21日金判1579号18頁)の判断
1 原審の判断の概要
原審は、会計限定監査役は、「会計帳簿の信頼性欠如が会計限定監査役に容易に判明可能であったなどの特段の事情のない限り、会社(取締役又はその指示を受けた使用人)作成の会計帳簿(会社法432条1項)の記載内容を信頼して、会社作成の貸借対照表、損益計算書その他の計算関係書類等を監査すれば足りる。」「会計限定監査役は、前記のような特段の事情がないときには、会社作成の会計帳簿に不適正な記載があることを、会計帳簿の裏付資料(証憑)を直接確認するなどして積極的に調査発見すべき義務を負うものではない。」との判断枠組みにより、本件においては会社の会計帳簿の信頼性欠如に関する特段の事情がないものとして、被告の損害賠償責任を否定しました。
2 原審の判断枠組みの問題点(会計監査実務の観点から)
原審の判断枠組みの理論的な問題については、弥永真生「会計限定監査役は会計帳簿の正確性をチェックしなくてもよいのか」金融・商事判例1582号2頁に詳細な記載があるためご興味がある方はこちらをご参照頂くこととし、本稿では、会計監査実務の観点から、原審の判断枠組みの問題点に触れることとします。
貸借対照表を含む計算書類には、会計帳簿で集計された各勘定科目の合計金額が記載されています。具体的には、会計システム上、総勘定元帳をベースとして各勘定科目の残高が集計され、これが残高明細表に記載され、残高明細表に記載された各勘定科目の残高が列挙された残高試算表に基づき、計算書類が作成されます。
現預金を例にすると、残高明細表には、各金融機関に対する当座預金、定期預金別の残高(A銀行当座預金 1000万円、B銀行定期預金 1000円)が列挙されて合計金額(2000万円)が記載され、残高試算表には、現預金勘定の残高として残高明細表の合計金額(2000万円)が記載されることになります。
会社が会計システムを利用していることを前提とすると、基本的に、会計帳簿の数字が自動的に計算書類に組み込まれることになるため、原審の判断によると、会計限定監査役がなすべき業務は相当程度限定されます。
すなわち、会計システムが総勘定元帳から各勘定科目の残高を集計して残高明細表・残高試算表・計算書類が作成されるため、会計限定監査役は、基本的に、残高明細表・残高試算表・計算書類の金額が一致することを念の為確認することによって業務が完了することになるためです(その前提として、経理担当者に対する質問等により、会計システムが適正に管理されているか否か、経営者・従業員による会計システムという内部統制の無効化リスクを検討することが必要となるように思われますが、原審の判断枠組みからすると、この検討すら必ずしも必要ないようにも読めます。)。
以上のとおり、原審の判断枠組みを前提とすると、会計限定監査役がなすべき業務が相当程度限定され、決算プロセスが会計システムに依拠する程度が大きい現代においては、その存在意義が極めて限定的になり得るという問題点があります。
ただし、現実問題として、中小企業における監査役(会計限定監査役)に対して、常に会計帳簿の金額の裏付を取ることを求めることはできず、一定の場合に限定して裏付資料の調査義務を課すという大枠自体は支持すべきものであると思われます(原審は結論の妥当性に重きを置きすぎた結果、会社法の理論上はやや無理のある判断枠組みを提示することになったということが言えるかと思います。)。
第4 最高裁判所の判断
1 本判例の判断の概要
本判例は、原審の判断枠組みを否定し、「監査役は、会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでなくとも、計算書類等が会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかを確認するため、会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め、又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合があるというべきである。…以上のことは会計限定監査役についても異なるものではない。」とし、「会計限定監査役は、計算書類等の監査を行うに当たり、会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても、計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば、常にその任務を尽くしたといえるものではない。」として、任務懈怠の有無等について審理をするよう、本件を原審に差し戻しました。
2 本判例の判断の留意点
SNS等において誤解があるところですが、本判例は、監査役(会計限定監査役)に対して、会計帳簿の基礎資料・裏付資料の調査を常に求めるものではありません。
すなわち、会社の内部統制の構築状況を踏まえて不正リスクを検討し、基礎資料を確かめるといった監査手続を取るべき場合に、然るべく手続を取ることを求めるにすぎず、このことは、「会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め、又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合がある」という判示に表れています。
一見すると、「会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め、又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合がある」という判示には歯切れの悪さがあり、「では、どの程度の監査手続が求められるのか。どのような場合に、基礎資料を確認する必要があるのか。」という疑問が湧いてくるところですが、それについて本判例は、明示的な答えを提供していません。
上記の問いに関連して、本判例は「被上告人が任務を怠ったと認められるか否かについては、上告人における本件口座に係る預金の重要性の程度、その管理状況等の諸事情に照らして被上告人が適切な方法により監査を行ったといえるか否かについて審理を尽くして判断する必要があり」としており、この判示が手掛かりとなります。この判示は、リスク・アプローチ、すなわち、財務諸表に重要な虚偽表示があるか否かについて意見表明を行うという会計監査の目的に照らして、当該会社の内部統制等を踏まえて重要な虚偽表示が生じるリスクを検討し、当該リスクが高い勘定科目等に監査資源を重点的に投下するという会計監査における基本的な考え方と整合します。
平たくいえば、本判例は、「リスク・アプローチに基づいて会計監査を遂行してください。全ての勘定科目について基礎資料を確かめろというつもりはありません(それが現実的ではないことはわかっています。)。会社の状況に応じて、会計上のリスクを検討して、重要な虚偽表示が起こる可能性のある勘定科目等についてはきちんと基礎資料の確認等の監査手続を実施してください。そういったリスク検討や状況に応じて必要となる基礎資料の確認等をしなかった場合には、責任を問われる可能性があります。」というメッセージを伝えていると言えるかと思います。
第5 本判例・原審の実務への示唆(特に職業専門家たる監査役に対する示唆)
税理士・弁護士等の職業専門家が、中小企業との付き合いで監査役を引き受けるケース、実質的な監査を行うことが必ずしも期待されていないケース、監査役を引き受ける職業専門家(あるいはその補助者)において会計監査の考え方や実務に必ずしも明るくないケースは現実に散見されるところであり、本稿は、そのようなケースについて一律に否定的な意見を述べようとするものでありませんし、また、本判例の事案がそのようなケースであったと述べるものでもありません。
以上の留保を前提として、職業専門家に対して社会から厳しい目線が向けられるようになりつつある現代において、従前のように、監査役を付き合いで、あるいは、名誉職として引き受けることのリスクは、高まっているものと言わざるを得ません。また、本判例は、被上告人の任務懈怠を認めたものではありませんが、高額な損害賠償を請求されること自体が、職業専門家にとって大きな負担となり、さらには、職業専門家を志す業界の担い手を喪失することにも繋がりかねません。
本判例が監査実務に対する警鐘であると受け止められ、監査役・監査役候補者が会計監査の知見を深めるきっかけとなることを願って、本稿の筆を置きたいと思います。
<バックナンバー>
- 2021-8-2 会計限定監査役の注意義務について原審の判断を破棄し差し戻した判例(最判令和3年7月19日) ―会計と法律の交錯を考える(3)―
- 2021-1-1 法務担当者が知っておくべき収益認識会計基準の基礎-会計と法律の交錯を考える(2)-
- 2020-13-1 内部統制の有効性の評価等の業務に関して監査法人の債務不履行責任を否定した裁判例(東京地判令和2年6月1日金融・商事判例1604号42頁)―会計と法律の交錯を考える(1)―
このリーガルノートに関連する法務
お問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ、ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。
松田綜合法律事務所
弁護士・公認会計士協会準会員
石畑智哉
info@jmatsuda-law.com
この記事に記載されている情報は、依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成されたものであり、教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報について法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう、また、個別な事実関係に基づく日本法または現地法弁護士の具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。