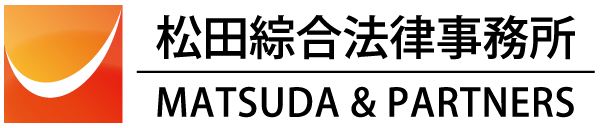M&P Legal Note 2020 No.13-1
内部統制の有効性の評価等の業務に関して監査法人の債務不履行責任を否定した裁判例(東京地判令和2年6月1日金融・商事判例1604号42頁)―会計と法律の交錯を考える(1)―
2020年12月14日
松田綜合法律事務所
弁護士・公認会計士協会準会員
石畑智哉
第1 はじめに
事業会社より一定の調査業務の委任を受けた監査法人が、当該業務の完了後に判明した事業会社内部での不正行為に関連した損害賠償責任を負うかが問題となった事案について、東京地方裁判所は、監査法人は損害賠償責任を負わないと判断しました(東京地判令和2年6月1日金融・商事判例1604号42頁)。
本件は、会計実務家が参照すべき裁判例であるとともに、事業会社においても、一定の業務を外部の専門家に依頼する際に留意すべき事項を示す裁判例でもあるため、本稿にてご紹介いたします。
第2 事案の概要
本件の事案の概要は以下のとおりです。
・原告(事業会社)は、平成26年6月30日の時点で、B社を含む子会社4社を有する、グループ会社の親会社であった。
・原告(事業会社)は、平成26年6月頃に、内部統制の有効性評価と企業価値算定を被告(監査法人)に(準)委任した(以下「本件契約」といいます。)。なお、本件契約に基づく具体的な委任事務の内容に争いがあり、それが本件での主たる争点となっている。
・被告(監査法人)は、同年7月中旬から同年8月上旬にかけて調査業務を行い、「内部統制の有効性評価と改善点」と題する書面(以下「本件報告書」といいます。)及び「企業価値算定書」(以下「本件算定書」といいます。)を作成し、同年9月1日頃、原告(事業会社)に対して交付した。
・甲野太郎氏(甲野)は、平成26年頃、原告(事業会社)の経理課に所属していた従業員であり、平成23年から同26年にかけて原告の子会社(B社)の監査役の地位にあった。甲野は、原告及び原告グループ会社の経理を任され、平成26年6月頃、原告及び原告グループ会社の代表印(実印)及び銀行員を全て保管していた。
・被告(監査法人)は、調査業務において、ゆうちょ銀行のB社名義の貯金口座(以下「本件口座」といいます。)について、甲野が提出した通帳のコピーに記載された預金金額とB社の会計帳簿上の金額が合致しているかを照合した。被告は、本件口座の残高証明書又は通帳の原本を確認してB社の会計帳簿上の金額と合致しているか否かの照合は行わなかった。
すなわち、被告は、
「本件口座の通帳のコピーに記載された預金金額=B社の会計帳簿上の金額」
であることを確認したものの、
「本件口座の残高証明書又は通帳の原本に記載された預金金額=B社の会計帳簿上の金額」
であるかどうかは確認しなかった。
・平成28年1月頃、甲野が、原告及び原告グループ会社から、数年間にわたり、金員を横領していたことが発覚した(以下「本件横領」といいます。)。なお、本件口座について甲野が被告(監査法人)に対して示した通帳のコピーは、甲野が作成した内容虚偽の偽造文書であった。
・原告(事業会社)は、被告(監査法人)は本件契約に基づいて金融機関の残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、その結果、甲野による本件横領を原告が覚知することができず原告に損害が生じたとして、被告に対する損害賠償請求を求めた。
第3 裁判所の判断
本件では、本件契約に基づく具体的な委任事務として、被告(監査法人)が金融機関の残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務を負っていたかどうかが主たる争点となりました。
裁判所は、被告が上記の義務を負っているかを判断するため、本件契約の委任事務の内容を確定した上で、委任事務の内容として、金融機関の残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務があったかどうかを判断しました。
結論として、裁判所は、被告は金融機関の残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務を負っていないとして、原告による損害賠償請求を認めませんでした。
1 本件契約に係る委任事務の内容
本件契約について、原告と被告の間で契約書が作成されていなかったことから、裁判所は、契約締結に至る経緯、調査業務の実施過程等に関する事実を認定した上で、「本件契約に係る委任事務は、被告が、原告及び原告グループ会社の内部統制の有効性評価及び原告の株式評価を行うことを内容とするものであった」と判示しました。
原告は、本件契約を締結する際、被告に対し、原告及び原告グループ会社に関する経理の調査確認ないし経理のチェックを依頼したと主張していましたが、この点については、調査業務の実施過程や本件報告書及び本件算定書の内容等を踏まえて、排斥されています。
さらに、原告は、本件契約を締結する際、被告との間で、預貯金の直接残高確認を行うことを特に合意したと主張していましたが、この点についても、原告の主張を裏付ける証拠資料が存在しないこと等から、排斥されています。
2 残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務の有無
裁判所は、内部統制の有効性評価に伴う義務又は企業価値評価に伴う義務として、被告が残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務を負っていたかどうかを検討しています。
(1) 内部統制の有効性評価に伴う義務
裁判所は、内部統制の有効性評価において被告が用いた手法について、「ウォークスルーの手法は、各子会社について1つの取引を追いながら、誤謬や不正取引が起きにくいチェック体制となっているか否かを確認する作業を行うことにより、内部統制手続をチェックする方法とされている」「上記の方法は、抽出した取引データが各部署に正確に伝達され、正しく取り扱われているかどうかを確認するものであって、当該取引データ自体の誤りを発見することには重点が置かれず、また、その分析に預貯金残高の情報は用いられない」とした上で「内部統制の有効性評価という観点からすると、収集した情報・資料を基に、実際の預貯金残高と帳簿残高の不一致が生じ得る仕組になっていないかを検証すれば足りる」「収集資料の正確性に具体的な疑義が生じているような状況でない限り、当該収集資料の作成に偽装、不正が介在しないことの検証までは求められていない」との判断枠組みを示しました。
そして、本件契約当時、原告及び原告グループ会社において、不正な経理処理がなされたとの具体的な疑義が生じていなかったため、本件においては、原告からの収集資料である通帳の写しを基に検証することも許され、被告が、残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務を負っていたとは認められないと判断しました。
(2) 企業価値評価に伴う義務
裁判所は、企業価値評価のプロセスに触れた上で、「数か月という比較的短期間のうちに結論を示すべき企業価値算定において、会計情報の信頼性の検証は算定目的の本質部分ではなく、しかもそれ自体財務諸表監査として企業価値算定に比べて長期の作業時間及び多額の費用を伴う依頼内容となり得るものであるから、別段の合意がない限り、評価対象会社から入手した資料に信頼性があると仮定して算定すれば足りる」と判示し、企業価値評価との関係でも、被告が、残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務を負っていたとは認められないと判断しました。
第4 本裁判例の位置づけ
1 会社と専門家の役割分担という視点
本裁判例は、監査法人が依頼者との契約において残高証明書又は通帳の原本を直接確認する義務を明示的に負っていないことを前提に、内部統制の有効性評価の実施について、原則として、依頼者からの提供を受けた資料に偽装・不正が介在していないという前提で業務を行うことができ、収集資料の正確性に具体的な疑義が生じているような例外的な状況において、依頼者から提供を受けた資料の作成に偽装・不正が介在しているかどうかの検証を行うべきことを示しています。
裁判所としては、監査法人を含む専門家は、契約で別段の定めがある場合や法令上の要請がある場合であれば格別、依頼者に係る一定の事項について業務を実施する場合、依頼者から提供を受けた資料が正確であるという前提で業務遂行することができるが、専門家を専門家たらしめる専門性に照らすと、依頼者から提供を受けた資料の正確性に具体的な疑義が生じているような場合には、仮に契約での別段の定めがなかったとしても、当該資料の正確性について慎重に検証しなければならないと考えているといえます。
上記の考え方は、会社作成の資料をもとに専門家が遂行する業務について、会社が資料を正確に作成し、専門家が当該資料を踏まえて専門的な見地から業務を遂行するという役割分担を前提として初めて成立するものであることを踏まえているといえます。会社作成の資料の正確性を前提とした専門家の業務遂行を許容しない場合には、専門家の負担が増大し、業務遂行が困難となるためです(また、専門家の負担が増大することの表裏として、依頼者の報酬面での負担が増大し、専門家への業務依頼が困難になるといった側面もあります。)。
2 本裁判例と関連する裁判例
会社と専門家の役割分担という視点が現れている裁判例として、東京高判令和元年8月21日金融・商事判例1579号18頁が挙げられます。当該判決は、会計限定監査役による監査について、会社法上、会計帳簿の正確性の確認を直接の任務とするものではないことを前提に、「会計帳簿の信頼性欠如が会計限定監査役に容易に判明可能であったなどの特段の事情のない限り、会社(取締役又はその指示を受けた使用人)作成の会計帳簿(会社法432条1項)の記載内容を信頼して、会社作成の貸借対照表、損益計算書その他の計算関係書類等を監査すれば足りる。会計限定監査役は、前記のような特段の事情がないときには、会社作成の会計帳簿に不適正な記載があることを、会計帳簿の裏付資料(証憑)を直接確認するなどして積極的に調査発見すべき義務を負うものではない。」として、会計限定監査役が監査を行う際に、原則として会社作成の資料(会計帳簿)を信頼することができるとしています。当該判決は、会計限定監査役による監査について、会社が正確な会計帳簿を作成し、会計限定監査役は会計帳簿が正確であることを前提に監査を実施するという役割分担を前提としているといえます。
また、東京高判平成20年5月21日判タ1281号274頁が、大規模な会社における取締役の善管注意義務に関して、下部組織が作成した資料について、取締役が当該資料の基になっている個別取引の詳細を一から精査することは現実的ではないことを踏まえて、取締役が当該資料に依拠することに躊躇を覚えるというような特段の事情のない限り、当該資料を基に調査・確認を実施すれば注意義務を尽くしたといえるとしたことも、本裁判例の考え方と同様の文脈で捉えることができます。すなわち、当該判決は、下部組織は資料を正確に作成し、取締役は当該資料を踏まえて、経営者としての知識・経験・英知に照らして業務を遂行するという役割分担なしに、会社の運営は成り立たないという会社経営の実情を反映しているものといえます。
第5 本裁判例の実務への示唆
1 事業会社の留意事項
事業会社が、一定の調査業務を外部の専門家に依頼する場合、①専門家が事業会社作成資料に偽装・不正等が介在していないことの確認することへの期待や②調査業務に関連した会社内部の不正については、当該調査業務にて明らかになることへの期待を有することはやむを得ないものと思われます。
しかしながら、本裁判例の考え方にもあるとおり、会社作成の資料を基に専門家が一定の調査業務を行う場合、会社は資料を正確に作成し、専門家は当該資料を踏まえて専門的な見地から業務を遂行するという役割分担が前提となっているため、契約書において、会社からの提供資料については専門家による原本確認を義務付けるといった特別の手当てを行わなければ、原本確認等をしなかったことに起因して専門家が会社内部の不正を見抜けなかったとしても、その責任を追及するのは困難であるといえます。
また、事業会社が一定の調査業務を外部の専門家に依頼する場合には、当該調査業務の目的や専門家への委任事務を契約書等で具体化・明確化し、委任事務の限界(例えば、当該委任事務によっては不正の発見は実務上困難であるなど)について専門家から十分な説明を受けた上で、当該調査業務の依頼を検討すべきといえます。
2 会計実務家の留意事項
本件が紛争化した根本的な原因は、原告が、仮に原告内部で不正があった場合には、内部統制の有効性評価、企業価値算定を通じて監査法人が当該不正を発見するであろうという期待を有していたことにあると推察されます(裁判所が、被告代表者は「原告代表者から、原告に不正がないかどうかの調査を要望されたものの、不正を発見するという調査は引き受けられないと応じる経過があった。」という認定をしていることからも、このような事情がうかがわれます。)。
不正の発見は財務諸表監査においても第一義的な目的ではなく、財務諸表監査はあくまで、経営者が作成した財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見表明をするものであることから、監査業務ではない内部統制の有効性評価等において、不正の発見が目的でないことは、監査法人には自明のことだといえます。
しかしながら、「監査対象に不正が存在したのに監査を実行しても不正を見抜けなかった場合に、監査役や公認会計士・監査法人は十分に職責を果たさなかったと考える向きが、それなりに多く存在するようである。」(金融・商事判例1579号20頁)との指摘があることからも、一般的に、監査法人による不正発見に対する期待は高く、監査以外の業務を受任する場合にもそのことを前提として、依頼者への事前説明、契約書での委任事務の内容の明確化等を行う必要があるといえます。
本件は、いわゆる期待ギャップ(社会が監査人に期待する監査の役割と、監査人が実際に遂行している監査の役割とのギャップ)に付随する問題といえ、期待ギャップの解消は、公認会計士にとって、今なお重要な課題であることを示す裁判例であるように思われます。
<バックナンバー>
この記事に関するお問い合わせ、ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。
松田綜合法律事務所
弁護士・公認会計士協会準会員
石畑智哉
info@jmatsuda-law.com
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成大手町ビル10階
電話:03-3272-0101 FAX:03-3272-0102
この記事に記載されている情報は、依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成されたものであり、教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報について法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう、また、個別な事実関係に基づく日本法または現地法弁護士の具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。
法律相談・お問合せ
松田綜合法律事務所
〒100-0004
東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成大手町ビル10階
電話:03-3272-0101
FAX:03-3272-0102
E-mail:info@jmatsuda-law.com