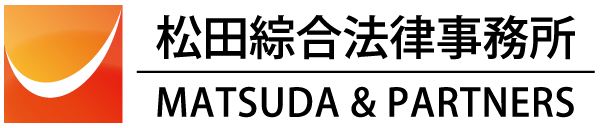M&P Legal Note 2025 No.8-1
医師及び歯科医師等の応招義務について
2025年8月8日
松田綜合法律事務所
弁護士 西村 隆(東京弁護士会)
1 応招義務の意義
医師法は、19条1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めており、また、歯科医師法は、19条1項において、「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めています。これらの医師及び歯科医師の義務は「応招義務」と呼ばれ、当該義務により医師及び歯科医師は、原則として診療拒否をすることができません。
2 応招義務の根拠
医師及び歯科医師の応招義務が定められていることの根拠は、医業の公共性や業務独占の反映としての診療義務から導き出されると一般に理解されています。
しかし、現代においては、医師法制定時(昭和23年)から医師の総数が大きく増加しており、また、医療機関の機能分化・連携や医療の高度化・専門化等により医療提供体制も変化しており、さらには勤務医の過重労働を解消するという「医師の働き方改革」の観点からの考慮も必要とされています。
このような医療を取り巻く状況の変化を踏まえて、診療の求めに対する医師・歯科医師の適切な対応の在り方を改めて整理する趣旨で、厚生労働省から「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日付け医政発1225第4号厚生労働省医政局長通知。以下「令和元年通知」といいます。)が出されています(その内容については後述します)。
3 応招義務の法的性質
応招義務(医師法19条1項、歯科医師法19条1項)は、医師又は歯科医師が、国に対して負担する公法上の義務であり、医師又は歯科医師の患者に対する私法上の義務ではありません。また、医師又は歯科医師が勤務医である場合に、応招義務を負うのは個人としての医師又は歯科医師です。
ただし、医療機関も、患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を行うことが求められ、正当な理由なく診療を拒んではならないとされています(「病院診療所の診療に関する件」(昭和24年9月10日付け医発第752号厚生省医務局長通知)。
4 応招義務違反の効果
応招義務の違反に対して、直接的に刑事罰を科す規定は定められていません。しかし、応招義務違反は、「医師としての品位を損するような行為のあったとき」(医師法7条1項)に該当するものとして戒告などの行政処分の対象となる可能性があります。もっとも、過去に応招義務違反のみを理由に行政処分がなされた実例は確認されていません。
5 診療拒否が正当化される場合の判断基準
医師若しくは歯科医師又は医療機関が、患者からの診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方として、令和元年通知は、患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)が最も重要な考慮要素であるとしています。また、医療機関相互の機能分化・連携や、医療の高度化・専門化等による医療提供体制の変化及び勤務医の勤務環境への配慮等の観点から、他に診療時間・勤務時間内であるか否か、及び患者と医師・歯科医師・医療機関の信頼関係についても重要な考慮要素であるとしています。
【令和元年通知における厚生労働省の判断基準】
| 緊急対応が必要な場合 | 緊急対応が不要な場合 | |
| 例 | 病状の深刻な救急患者等 | 病状の安定している患者等 |
| 診療時間内・
勤務時間内 |
・原則として診療しないことは正当化されない。
・専門性、医療提供の可能性、医療の代替可能性等を総合勘案し、事実上診療が不可能な場合のみ診療しないことが正当化される。 |
・原則として必要な医療を提供する必要がある。
・専門性や医療提供の可能性、医療の代替可能性、患者との信頼関係等を考慮し緩やかに解釈される。 |
| 診療時間外・
勤務時間外 |
・応急的に必要な措置をとることが望ましい。
・原則として診療しないことについて、法的責任を問われることはない。 |
・即座に対応する必要はなく、診療しないことは正当化される。
・時間内の受診依頼、他の診察可能な医療機関の紹介等の対応をとることが望ましい。 |
6 診療しないことが正当化される具体例
上記5の判断基準を踏まえ、厚生労働省は、具体的な事例に関して、患者を診療しないことが正当化されるか否かについて以下の通り示しています。
【令和元年通知における厚生労働省の整理】
| 個別事例 | 患者を診療しないことが正当化されるか否か |
| 患者の迷惑行為 | 迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には正当化される(診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等)。 |
| 医療費不払い | ・医療費の不払いのみをもって診療しないことは正当化されない。
・支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて医療費を支払わない場合等には正当化される。 |
| 入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等 | ・医学的に入院の継続が必要ない場合には、通院治療等で対応すれば足りるため、退院させることは正当化される。
・病状に応じて高度な医療機関から地域の医療機関へ紹介し、転院することも原則として正当化される。 |
| 差別的な取扱い | ・患者の年齢、性別、人種・国籍、宗教等のみを理由に診察しないことは正当化されない。
・言語が通じないことや宗教上の理由等により結果として診療行為が著しく困難な場合には正当化される。 ・法令上特定の医療機関で診療することが定められている感染症以外の特定の感染症へのり患等の、合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。 |
| 訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者への対応 | ・原則として日本人患者の場合と同様に判断する。
・文化の違い、言語の違い、本国に帰国することで医療を受けることが可能であること等のみをもって診療しないことは正当化されない。 ・文化や言語の違い等により、結果として診療行為そのものが著しく困難である場合には診療しないことが正当化される。 |
7 不法行為及び債務不履行責任の成否
応招義務は、上記の通り、医師法上(公法上)の義務であり、応招義務を規定する医師法19条1項は、直接、患者に対し診療を請求する権利を認めるものではありませんので、医師及び歯科医師並びに医療機関の民事上の義務については、別途検討する必要があります。裁判所は、医師若しくは歯科医師又は医療機関の不当な診療拒否に対しては、医師若しくは歯科医師又は医療機関の、患者に対する債務不履行責任(民法415条)又は不法行為責任(民法709条、715条)を根拠として、患者からの損害賠償請求が認められると判断しています。
従来の裁判例では、医師の診療拒否が、不法行為等に該当するか否かについては、医師法19条1項の趣旨を踏まえて社会通念に照らして判断すべきであるとされています(歯科医師及び医療機関も同様と考えられます)。具体的には、①緊急の診療の必要性の有無、②他の医療機関による診療可能性の有無、③診療拒否の目的・理由の正当性の有無等の事情を総合考慮して判断すべきであるとされていますが、これらの判断基準は、基本的には厚生労働省の令和元年通知が示す判断基準と同様の考え方に立つものといってよいと考えられます。
8 診療を拒否する場合の留意点
医療機関においてよくみられる、迷惑行為を繰り返す患者の診療を拒否するケースを例に、対応に際しての主な留意点をご説明します。
① 診療拒否の正当化事由の検討
診療拒否による応招義務違反や民事上の責任を問われないために、患者の迷惑行為の態様・程度、常習性、医療機関の被害の状況などを勘案しつつ、上記の令和元年通知や裁判例の判断基準に照らして、診療拒否が正当化されるかについて十分な検討が必要です。特に緊急対応が必要な患者(病状が深刻な患者)に対しては、慎重な検討が必要です。医学的な合理性については、複数の医師により医療機関として判断することが望ましいと考えられます。また、医療法務に詳しい弁護士等の専門家に相談することも有益です。
② 客観的証拠の記録化
患者の迷惑行為について、日常的に診療記録や看護記録等に5W1Hに基づき詳細に記録しておくことや、必要に応じて会話や電話を録音し、迷惑行為を防犯カメラで録画しておくことも有効です。これらは、万一、警察へ被害届を提出する際や裁判において証拠として使用することができます。
③ 対応窓口・体制の明確化
患者に対する窓口を定めて対応を一本化しつつ、当該患者に関係する医師や看護師、事務長・事務職員等の間で、事実関係や医療機関としての決定方針等について情報共有を十分に行うことも重要です。
以上