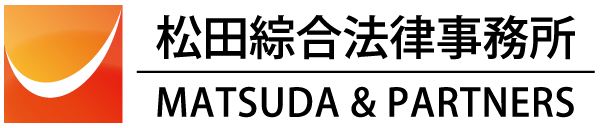M&P Legal Note 2025 No.10-1
医師の説明義務について
2025年10月10日
松田綜合法律事務所
弁護士 西村 隆(東京弁護士会)
1 説明義務の意義
医療法1条の4第2項は、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならない。」と定めています。本規定では、説明義務は法的拘束力のない努力義務として定められていますが、今日、多くの医療事故訴訟において、医師の医療行為上の過失とともに、あるいは単独で医師の説明義務違反が主張されており、判例上、医師が患者に対して説明義務を負うことは確立されています。
2 説明義務の類型
説明義務を以下の3類型に分ける考え方などがあります。
①患者が自己決定するための説明義務(患者の同意を得るための説明義務)
②療養方法の指導としての説明義務(患者に対する指示)
③治療等が終了した時点における説明義務(顛末報告義務)
上記のうち、説明義務とは①を指すのが通常であるため、本稿では①についてのみご説明します。
3 説明義務の根拠
患者は自らの生命や身体について自ら決めることができる権利(自己決定権)を有しており、患者の自己決定権を保証するために、医師が説明義務を負うと考えるのが最近の有力な見解です。医師から診療に関する情報提供を受けなければ、患者は適切に自己決定権を行使することはできないからです。もっとも、裁判所は、医師の説明義務の根拠を患者の自己決定権ではなく、診療契約上の義務ととらえていると考えられています。
4 説明の相手方
医師の説明義務は、患者の自己決定権を保証するためのものであるため、説明の相手方は原則として患者本人となります。
ただし、患者が、未成年者である場合、意思能力若しくは行為能力を有しない成人である場合又は意識不明の者である場合等には、説明義務を尽くすために、基本的には以下のとおり対応すべきと考えられます。
| 患者の状況 | 説明の相手方 | |
| 未成年者 | 原則として親権者に対して説明する。未成年者本人にも説明する必要がある場合も考えられる。 | |
| 意思能力又は行為能力を有しない成人 | 成年後見人あり | 原則として成年後見人に説明する。 |
| 成年後見人なし | 成年後見人に代わる近親者へ説明する。 | |
| 意識不明者 | 説明が可能となってから患者本人に説明する。 | |
上記のうち患者に代わり成年後見人に説明すべき場合に、成年後見人に迅速に説明することが困難なときは、一定の親族関係がある患者の付添人に説明をすることで足りると考えられています。また、患者本人の意思能力が十分でなく、代わりに説明すべき相手が容易に見つからない場合に緊急の医療行為を要するときは、説明をせずに医療行為を行ったとしても、説明義務違反とはならないと考えられています。
5 説明の方法
医師の説明義務が、患者の自己決定権を保証するためのものであることからすれば、患者が自己の身体にどのような医療行為を行うか決定するために、説明内容を十分に理解可能な方法で説明を行うべきです。したがって、同意書などを患者から徴求するだけでは不十分であり、通常は医学の専門知識を有していない患者でも理解できるように、説明書等の文書において分かり易い説明を記載しつつ患者に交付し、口頭でもその要点について説明を補足して、患者が十分に理解しているか確認すべきことになります。
他方で、後日、患者から医療事故訴訟を起こされた場合に備え、説明義務違反の責任を免れるための証拠とするため、カルテにおいて患者に説明書等を交付し口頭でも補足説明を行った旨とその説明の内容、質疑応答の内容及び説明した日時・場所・相手方等を記録しつつ、患者に交付した説明書等とともに患者の署名押印のある同意書を添付し保管しておく方法がよいと考えられます。
また、患者が説明を受けることを拒絶している場合には、説明をしなかったとしても説明義務違反を問われることはないと考えられますが、後日、患者又はその遺族が説明を受けていないとして紛争となるおそれがあります。そこで、説明を受けることを拒絶している患者に対しても、説得して必要最小限の説明をするか、その家族などの付添人に対して説明をすることが必要と考えられます。
他に、緊急状態など説明のための時間的余裕がない場合、患者が説明内容について既に十分な知識を有している場合、医療行為に伴う危険性が顕在化する危険が極めて小さい場合又は医師に法律上強制的な医療行為を行う権限が認められている場合等においても、説明義務が免除又は軽減されると考えられています。このような場合にも、やはり後日の紛争防止の観点からは、必要に応じて事実関係を証拠化しておくことがよいでしょう。
6 説明すべき事項
医師が説明すべき事項については、診療内容、患者の容体、疾病の種類及び診療の段階等の具体的事実関係を勘案しつつ、個別に判断せざるを得ませんが、以下の判例の基準及び厚生労働省の指針が参考になります。
【手術に際して説明すべき事項の範囲に係る判例の基準】
| 最高裁判決平成13年11月27日(民集55巻6号1154頁)
・ 当該疾患の診断(病名と病状) |
【厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年9月12日)】
| ① 現在の症状及び診断病名 ② 予後 ③ 処置及び治療の方針 ④ 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用 ⑤ 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それぞれの場合の費用を含む) ⑥ 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無 ⑦ 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合にはその旨及び目的の内容 |
7 説明の程度
説明義務の程度に関しては法律学上の学説の対立がありますが、裁判所は、特定の学説によらずに、個々の具体的事実関係に基づき判断しています。最高裁判所で説明義務の有無が争われたケースにおける裁判所の判断枠組みを整理すると以下のとおりです。
| 類型 | 説明すべき内容 |
| 医療水準として確立した療法が複数ある場合 | 最高裁判決平成13年11月27日(民集55巻6号1154頁)
・ 患者がいずれの療法を選択するかを判断できるような仕方で、療法の違いや利害得失を分かり易く説明する。 最高裁判決平成17年9月8日(判例タイムズ1192号249頁) ・ 患者が療法に関する強い希望を有している場合は、当該希望にも配慮した説明が必要である。 |
| 選択肢として未確立の療法がある場合 | 最高裁判決平成13年11月27日(民集55巻6号1154頁)
・ 未確立の療法について、一般的には説明義務を負わない。 ① 未確立の療法が少なからぬ医療機関において実施されていること |
| 選択肢として予防的療法の実施と保存的経過観察がある場合 | 最高裁判決平成18年10月27日(判例タイムズ1225号220頁)
各予防的療法の違いや、経過観察も含めた各選択肢の利害得失について分かりやすく説明する義務がある。 |
8 説明義務違反の法律効果
説明義務違反がなければ患者は当該医療行為を受けていなかったことを患者が証明すると、説明義務違反と患者の死亡や身体の障害等との間に因果関係が認められ、説明義務違反をした医師は損害賠償責任を負わなければならないことになります。例えば、予防的治療として手術を実施する際に、適切な説明が行われていれば、患者はその手術を受けることはなかったと考えられ、死亡等の結果も生じなかったという場合です。この場合、裁判例は、たとえ医療行為に過失がなかったとしても、医療行為に過失があった場合と同様の損害賠償責任を認めています。
他方で、患者が上記の証明をすることができなかった場合は、説明義務違反と死亡や身体の障害等との間に因果関係は認められず、説明義務違反により患者の自己決定権が侵害されたとして、その慰謝料のみが認められることになります。当該慰謝料の額は、説明義務違反の程度や医療行為によって生じた結果(死亡や身体の障害)等に基づき個別の事案ごとに総合的に判断されます。この場合、医療事故訴訟において認められる慰謝料の額は、比較的少額にとどまります(通常は数十万円から200万円程度といわれています)。
なお、多くの医療事故訴訟において、患者側は、医療行為上の過失と説明義務違反の双方を主張しますが、医療行為上の過失により患者が死亡したと認められ、患者の死亡による逸失利益等の損害賠償請求が認められる場合には、通常、説明義務違反の点は判断されないことになります。
以上の点を、患者が死亡したケースを例に整理しますと下表のとおりとなります。
| 説明義務 | 医療行為上の過失 | 死亡の結果
との因果関係 |
死亡の場合の
責任内容 |
| 説明義務違反あり | 過失有り | 有り | 休業損害、逸失利益、慰謝料等の損害賠償 |
| 過失無し | 有り | 休業損害、逸失利益、慰謝料等の損害賠償 | |
| 無し | 自己決定権侵害による慰謝料の賠償のみ |
以上のとおり、たとえ当該医療行為が医療水準にかなったものであって、医療行為上の過失がなかったとしても、患者の死亡や身体の障害等の結果が発生した場合には、説明義務違反が認められると一定の損害賠償責任を負わなければならないことに注意が必要です。
以上