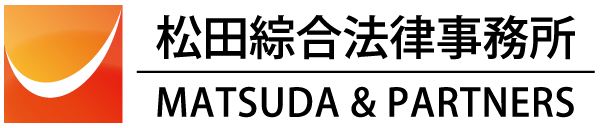M&P Legal Note 2019 No.9-1
マタハラを巡る訴訟において、労働者側が逆転敗訴し、記者会見における労働者の発言が名誉毀損と認定された事件(ジャパンビジネスラボ事件)
2019年12月13日
松田綜合法律事務所
弁護士 柴田政樹(東京弁護士会)
1 はじめに
語学スクールを運営する会社(以下、「Y社」といいます。)で正社員として雇用されていた女性従業員(以下、「Ⅹ」といいます。)について、育児休業後に有期労働契約への変更がなされ、その後に、雇止めが行われたという事案について、東京高等裁判所は、2019年11月28日に、雇止めは有効であり、本件従業員が行った記者会見を会社に対する名誉毀損と認定し、本件従業員に55万円の損害賠償責任を認めました。これは、雇止めを無効と判断した第一審(東京地判平成30年9月11日)の判断を覆すものです。
本件は、マタニティハラスメントを巡り、雇止めの効力や損害賠償責任が争われた事案について、第一審と第二審とで判断が分かれており、注目に値しますので、ご紹介します。
2 事実経緯
本件の事実経緯は、以下の通りです。
| 年月日 | 出来事 |
| 2008.7 | XとY社との間で、正社員としての無期労働契約(本件正社員契約)を締結 |
| 2013.3.2~ | Xが子を出産
育児休業を開始(子の保育園が決まらず、育児休業を6ヶ月延長) |
| 2014.2.22 | XとY社代表者等との間で面談を実施(Y社代表者等が、①正社員として従前と同様の勤務、②正社員としての時短勤務、③契約社員への変更の、3つの選択肢があることを説明) |
| 2014.9.1 | Xの育児休業が終了(子の保育園が決まらず)
XとY社との間で、期間1年かつ週3日勤務の契約社員を内容とする労働契約(本件契約社員契約)を締結(本件正社員契約から本件契約社員契約への変更を、「本件合意」といいます。) |
| 2014.9.2 | Xが契約社員として職場復帰 |
| 2014.9.9 | XがY社に対し、子を入れる保育園が見つかったので正社員への変更を求めるも、Y社は、これに応じず |
| 2015.5.29 | Y社が、正社員の地位不存在確認の労働審判手続きを申立てる |
| 2015.7.31頃 | Y社がXに対して、本件契約社員契約を更新しない旨の通知を行う |
| 2015.8.1 | Ⅹが、労働審判手続きの申立てを取り下げる |
| 2015.8.3 | Y社がXに対して、雇用関係不存在確認を求めて訴訟提起する |
| 2015.10.22 | XがY社に対して、雇用関係確認等を求めて訴訟提起をする
Xが、本件に関する記者会見(本件記者会見)を行う |
| 2016.9.26 | Y社がXに対して、本件記者会見が名誉毀損であるとして損害賠償請求の反訴を提起 |
| 2018.9.11 | 第一審(東京地裁)が、判決を下す
・雇止め無効(賃金請求を認容) ・Y社に、100万円の損害賠償責任を肯定 |
| 2019.11.28 | 第二審(東京高裁)が、判決を下す
・雇止め有効(賃金請求を棄却) ・Xに、55万円の損害賠償責任を肯定 |
3 本件の争点と裁判所の判断
(1) 概要
本件の争点は、大きく分けると、①本件合意の内容及び有効性、②雇止めの有効性、③Y社の損害賠償責任(契約準備段階の信義則違反行為)の有無、④Xの損害賠償責任(名誉毀損行為)の有無の4点です。
これらの点についての、第一審(東京地裁)と第二審(東京高裁)の判断の概要は、以下の通りです。
| 第一審
(東京地裁) |
第二審
(東京高裁) |
|
| ①本件合意の内容及び有効性 | ・本件正社員契約の解約
・有効 |
同左 |
| ②雇止めの有効性 | ・無効 | ・有効 |
| ③Y社の損害賠償責任(契約準備段階の信義則違反行為)の有無 | ・Y社に110万円の損害賠償責任を肯定 | ・Y社の損害賠償責任を否定 |
| ④Xの損害賠償責任(名誉毀損行為)の有無 | ・Xの損害賠償責任を否定 | ・Xに55万円の損害賠償責任を肯定 |
以下では、上記①から④について、争点の具体的内容と裁判所の判断内容をご説明します(ただし、第二審(東京高裁)の判決内容の全文を確認できていないため、推測が入る部分もありますことは、ご留意下さい。)。
(2) ①本件合意の内容及び有効性
本件の事実経緯に記載した通り、XとY社との間では、育児休業からの復帰後に、期間1年かつ週3日勤務の契約社員とする労働契約(本件契約社員契約)が締結されており、契約書も取り交わされています。Y社としては、この契約書の取り交わしにより、本件合意(すなわち、本件正社員雇用契約を解約し、新たに本件契約社員契約を締結する旨の合意)が成立したものと認識していました。
これに対し、Xは、本件合意について、(ⅰ)本件正社員雇用契約を解約する趣旨の合意ではなく勤務時間を減らす合意に過ぎないこと、(ⅱ)雇用機会均等法9条3項[1]及び育児介護休業法10条[2]の妊娠・出産・育児休業等の取得を理由とする不利益取扱いに該当するため無効であること、(ⅲ)自由な意思に基づく同意が存在しないこと、(ⅳ)錯誤無効であること、の反論を行いました。
第一審(東京地裁)は、Xの反論を排斥し、本件合意により、有効に、本件正社員契約は解約され、新たに本件契約社員契約を締結されたものと判断しました。
Xの反論ごとの裁判所の判断の詳細は割愛させていただきますが、上記(ⅲ)については、労働条件の変更に関わる合意は、書面の取り交わしがあっても、その合意の効力が否定されることがあるため、予防労務の観点からは、書面を取り交わすだけではなく、十分な説明を実施しておくことが重要です。本件において、第一審(東京地裁)は、結論として、合意の有効性を肯定しましたが、これが労働者の自由な意思に基づくものといえるか否かについて、詳細に事実認定をした上で判断していることには注意が必要です。
なお、裁判所が認定した事実によれば、Y社は、Xに対し、本件合意を締結する前に面談の機会を設け、選択肢を提示した上での説明をしており、使用者側の対応として参考になります。
第二審(東京高裁)も、この点は同様の判断をしているようです。
(3) ②雇止めの有効性
Y社は、雇止めの理由として、(ⅰ)Xが本件合意についての自己の主張に固執してY社を誹謗中傷したこと、(ⅱ)マスコミに対してY社からマタニティハラスメントを受けたとの虚偽の事実を吹聴したこと、(ⅲ)職場内において無断録音を繰り返し、Y社代表者から退社を命じられてもこれに応じず、Y社代表者を追いかけるなどの異常な行動をしたこと、(ⅳ)就業時間内に業務外の電子メールを作成・送信したこと、(ⅴ)被告に社会的制裁を加えるために被告に在籍している旨を述べて職場秩序を乱したことなどを主張しました。
これに対し、第一審(東京地裁)は、Y社主張の雇止めの理由のうち、客観的に合理的な理由に当たり得るのは、上記(ⅲ)及び(ⅳ)のみであるが、これだけでは客観的に合理的な理由が十分にあるとはいえず、雇止めは無効であると判断しました。(ⅲ)無断録音に関し、第一審(東京地裁)は、使用者の録音禁止命令は、録音されることにより被告の経営上の秘密やノウハウ等の情報が社外に漏えいすることを防止する場合に合理性が認められるものであること、録音が労使間の紛争において重要な証拠になり得るものであること、無断録音行為によってY社に損害が生じたわけでもないことなどを理由に、その当否の問題はあるにせよ、客観的に合理的な理由とはいえないと判断しています。
他方、第二審(東京高裁)は、雇止めを有効と判断しており、第一審の判断を覆しました。録音禁止命令が許容されるとした上で、Xの無断録音行為は、服務規律に反し、円滑な業務に支障を与える行為と認定したようです。
録音禁止命令の有効性を巡っては、近年の裁判例[3]において、使用者は労働者に対し、労働契約上の指揮命令権及び施設管理権に基づき職場の施設内での録音を禁止する権限があり、無断録音が行われると職場内で自由な発言ができなくなることにより職場環境が悪化するなどの実害が生じることがあるとの判断がなされています。
第二審(東京高裁)は、録音禁止命令について、被告の経営上の秘密やノウハウ等の情報が社外に漏えいすることを防止することのみならず、上記裁判例のように、無断録音による職場環境悪化も録音禁止命令の合理的理由になると判断したものと考えられ、この点で第一審(東京地裁)と判断が分かれたものと思われます。
(4) ③Y社の損害賠償責任(契約準備段階の信義則違反行為)
Xは、妊娠、出産、育児休業を経たXをY社が嫌悪し、排除するために嫌がらせを重ねて、雇止めをしたものであり、これらはマタニティハラスメントに当たる不法行為であるとして、慰謝料及び弁護士費用の合計330万円の損害賠償請求を主張しました。
第一審(東京地裁)は、Xが正社員復帰を申し出たことによって「正社員への契約再変更」に向けた準備段階に入っており、このような契約準備段階において交渉に入った当事者間では、誠実に交渉を続行して一定の場合には重要な情報を相手方に提供する信義則上の義務を負い、これに違反した場合には不法行為に基づく損害賠償責任を負うとしました。その上で、本件については、Y社は、多様な働き方を希望するXに対して、これに誠実に向き合うどころか、Y社の考えや方針のもとにXの考えを曲げるように迫るなどしたものであると認定し、Yに慰謝料等として100万円の支払を命じました。
他方、第二審(東京高裁)は、第一審の判断を覆し、Xの損害賠償請求を棄却したようです。③Y社の損害賠償責任の有無は、②雇止めの有効性の判断と実質的にリンクするものと思われますので、判断が分かれた理由もここにあるものと思われます。
(5) ④Xの損害賠償責任(名誉毀損行為)
Xは、2015年10月22日に、厚生労働省記者クラブにおいて、記者会見を開き、Y社の名称を公表して、訴訟提起を行ったことを述べ、Y社代表者等から出産を機に、退職勧奨、雇止め、人格否定等をされたとの発言をしました(本件記者会見でのXの言動としては、「子供を産んで戻ってきたら、人格を否定された」、「原告が、労働組合に加入したところ、「あなたは危険人物です」と発言された」などがあります。)。
Xの上記言動について、Y社は、上記の記者会見におけるXの言動は、Y社代表者らが妊娠・出産・育児休業を経て復職する従業員に対して、いじめや嫌がらせ、退職強要などのマタニティハラスメントを行う企業であるという評価をY社の従業員や顧客を含めた社会一般に与え、社会評価や名誉・信用を毀損するものであるとして、慰謝料及び弁護士費用の合計330万円の請求をしました。
第一審(東京地裁)は、記者会見におけるXの発言は、訴訟の一方当事者の一方的な言い分と受け止められることは明らかであって、これのみによってY社の名誉や信用が毀損される行為ではなく、仮に、Y社の名誉や信用が毀損されたとしてもそれは報道機関の報道の仕方によるか、又は報道を見聞きした者の偏った受け止め方によるものであり、Y社の請求は認められないと判断しました。
他方、第二審(東京高裁)は、第一審の判断を覆し、記者会見におけるXの発言内容は、客観的事実と異なり、名誉毀損に当たると認定し、Xに慰謝料等として55万円の支払を命じたようです。
4 最後に
本件については、今後、最高裁判所による判断がなされるものと思われます。第一審と第二審とで判断が分かれていることもあり、最高裁の判断に注目が集められます。
特に、職場内における録音禁止について、最高裁が、これを広く許容する方向で判断をするのか、それとも、これを制限する方向で判断をするのかは、今後の労使紛争におけるプラクティスにもかかわる重要な論点です。近年の労使紛争(特に、ハラスメントや退職勧奨が争われる例)においては、労働者側から証拠として録音が提出されることが一般化しており、労働者側からは、録音禁止命令を広く許容することは、労働者の立証を困難にするものであるとの指摘がなされています。
筆者としては、無断録音によって職場内での自由な発言が抑制されてしまうことは使用者にとって看過できない問題であるため、使用者には、職場環境維持のために、労働契約上の指揮命令権等に基づいて職場内での録音を禁止する権限があると考えます。この点を明確にしておくためには、就業規則において無断録音を禁止する旨を明記することも検討に値します。
なお、仮に録音禁止命令を出していても、労働者が録音をしている場合において、これが証拠として提出されるという可能性は残りますので、リスク軽減の観点からは、退職勧奨や面談等の場面では、録音がなされている可能性も念頭においた上で、丁寧な対応をすべきです。
[1] 男女雇用機会均等法9条3項は、「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法…第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定めています。
[2] 育児介護休業法10条は、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定めています。
[3] 東京地裁立川支判平成30年3月29日(甲社事件)。
<参考>
松田綜合法律事務所の人事労務情報ブログ
https://labor-law.jp/人事・労務に関する最新の法律情報、法改正、裁判情報などを弁護士がわかりやすく解説しています
この記事に関するお問い合わせ、ご照会は以下の連絡先までご連絡ください。
松田綜合法律事務所
弁護士 柴田政樹
info@jmatsuda-law.com
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成大手町ビル10階
電話:03-3272-0101 FAX:03-3272-0102
この記事に記載されている情報は、依頼者及び関係当事者のための一般的な情報として作成されたものであり、教養及び参考情報の提供のみを目的とします。いかなる場合も当該情報について法律アドバイスとして依拠し又はそのように解釈されないよう、また、個別な事実関係に基づく日本法または現地法弁護士の具体的な法律アドバイスなしに行為されないようご留意下さい。